藤枝市の瀬戸川を先輩と歩いた。
台風の影響で風が強い。それを楽しむかのように優雅に舞うトビをしばらく眺めていた。
ここ最近増えたという白い彼岸花。シロバナマンジュシャゲ。ネット情報によると、原種の赤に黄を交配したもののらしい。瀬戸川のシロバナマンジュシャゲは自然交配なのか、誰かが球根を植えたのか。
彼岸花は「全草にアルカロイドのコリンなどが含まれ、嘔吐、腹痛、下痢のほか、重症化すると中枢神経系に障害を起こす」(「身近にある うまい雑草、ヤバイ雑草」森昭彦,SBクリエイティブ,2025)
はるか昔に、農地のモグラ対策で植えられたという話を何かの本で読んだことがある。アルカロイドは水性なので、水で毒抜き処理をすれば、飢饉の際の非常食になるとも。
「昔、墓地にも植えたね」と先輩が呟いた。

「これがムクノキだよ」散歩の目的は木の実を食べること。
それにしても91歳とは思えない人で、いつも感心する。

しかし真っ先に目に飛び込んできたのはカメムシ。2センチを超えるキマダラカメムシ。
「スウェーデンの博物学者カルル・ペーテル・ツュンベリーが1770年代に長崎の出島で採集し、1783年に新種として記載した後、約150年間再発見されなかったが、近年分布が拡大している」という。(「日本原色カメムシ図鑑」友国雅章/監修,全国農村教育協会,1993)
カメムシには美しいものが多い。タマムシの厨子というものがあるが、カメムシを工芸に使うことができないだろうかと前から考えている。

大きなムクノキ

青い実が少しある。大きさはブルーベリーくらい。

熟すとブルーベリーの色に。
先輩が次々と口に入れるのをしばし見てから、恐る恐る口に入れて噛む。
凄い甘味。甘ったるい。今度糖度を測ってみようかな。

次は隣のエノキの実。スマホカメラには全景が入りきらない。

ムクノキの実より二回り小さい。甘味はそれほどないが、私は甘ったるいムクノキの実より、エノキの実の方が好きだ。先輩と意見が分かれた。
口の中でポロポロとほぐれ、何かの和菓子を食べているような感じがした。

家に帰って写真を見て、あらためてこの二つの木はそっくりだと思った。
調べるとやはり同じ「アサ科」に属していた。「山渓カラー名鑑 日本の樹木」山と渓谷社,1985ではニレ科に分類されているが、その後分類が変わったようである。(「山渓ハンディ図鑑14 増補改訂 樹木の葉」山と渓谷社,2020)
葉もそっくりだが、ムクノキは鋸歯が全体にあるのに対し、エノキの鋸歯は先半分と図鑑にある。しかしエノキも幼木の葉は全体にあり、冷温帯に自生するエゾエノキも同様なので、花や実がない時期の見分けは難しいのではないか。樹皮で見分ける方法もある(エノキは樹皮が裂けない)ようだが、それはこの次に確認しよう。
「家の裏にアケビが成るから食べるかい?」と聞かれ、お願いしておいた。
10年ほど前、定宿の民宿で朝食にアケビを添えてくれ、種までぼりぼりと噛み砕いたら急に気分が悪くなり体を起こしていることができなくなった。その原因はいまだにわからないが、今度は慎重に実だけを食べることにしようと思っている。
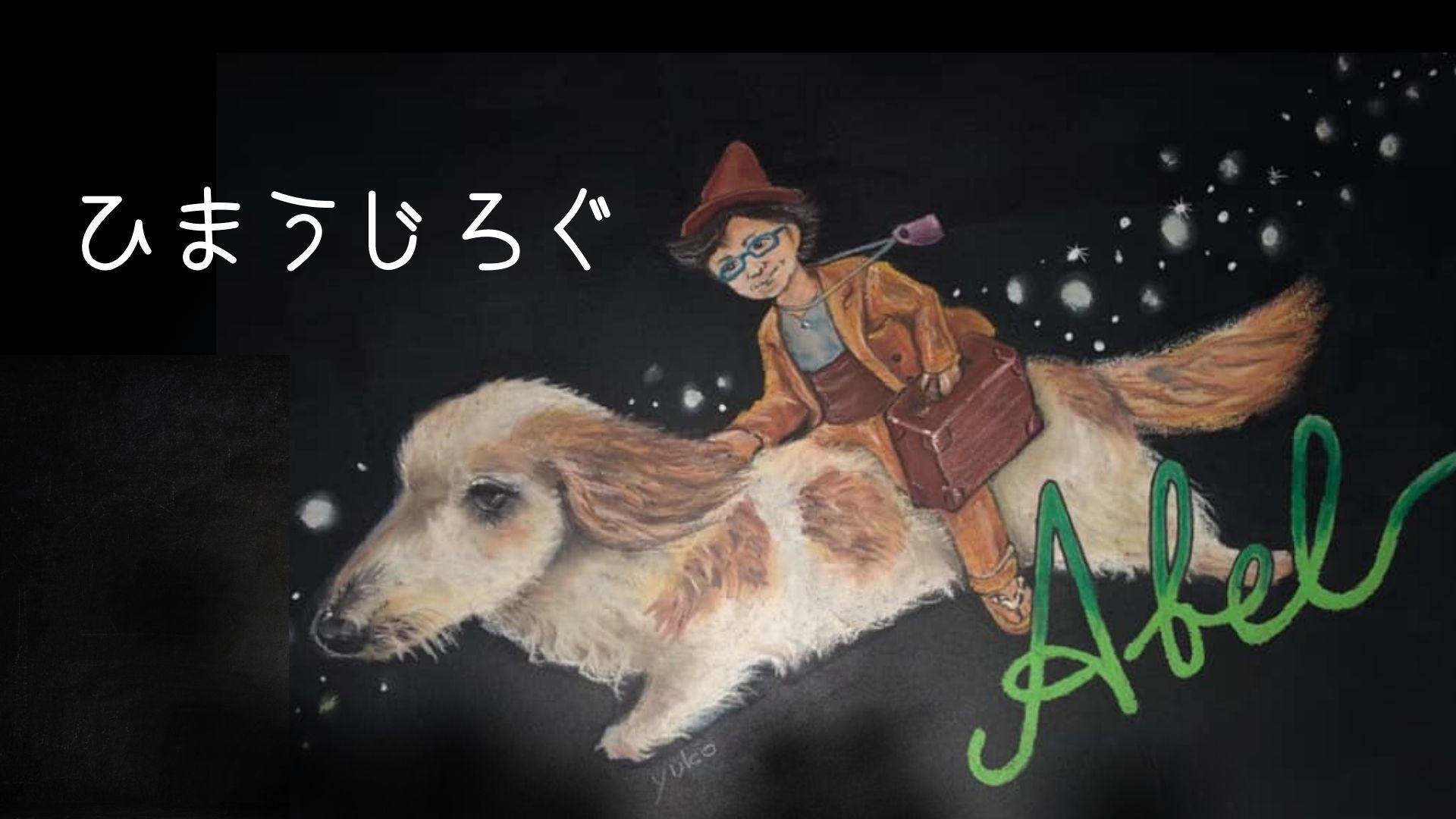



コメント