2月初めにコペンを注文し、5月中旬に納車された。工場の火災で1か月遅れた。
待ち遠しくて納車前に作ったのが、ドライビング・グラブ。
納車後、最初に作ったのは鍵のカバー。シリコンカバーをハードストックで購入。緑のヌメ革にアクリル絵の具で「COPEN]と書いてみた。色移りしないよう、塗料でコーティング。

次にハンドル中心部のダイハツのマークに赤い革を貼った。

飲み物を置くところなどに、ステッチを入れた革を貼った。まずは簡単なところから。飲み物の水分で革が変色してしまうだろうが、実際に飲み物をここに置くことはないので大丈夫。

カーナビ周りも地味なので、縁をつけた。型紙を作るのが意外と難しい。少し曲がっているところに、手作り感が溢れている。

この型紙は、穴の位置どりが難しかった。何度か失敗して、これでよしとした。

ここは両側がピッタリ合っていないけれどよしとした。これをベースにもう一度作ればピッタリになるけど。

ダッシュボードの取っ手はおまけのような感覚で、ささっと作った。

ここにも革を貼ることにした。

ウインド・ディフレクターに何か飾りが欲しいと思い、革を切って貼った。LED発光のウインド・ディフレクターが市販されているけれど、夜間目立ちすぎるため、地味コペン派の私は購入を断念。

シートベルトにも飾りつけ。これからベルトを覆うクッションカバーを作ろうと思っている。

ハンドルカバーは難しくて一度失敗している。外径と内径の長さが異なりどうするか考えたが、長さを変えず長方形の革をハンドルにぐるりと一周巻いてみた。すると内側に皺が寄ってしまった。考え方を変え、ハンドルをぐるりと一周巻くのではなく、6割ほど覆うだけにした。革の形は長方形のまま、内側にワイヤーを入れて絞った。ワイヤーを通して固定する金具をハードストックで購入。2本のワイヤーを通し金具を押し潰して完全固定しまうものと、ネジを締めて固定する脱着可能なものがあり、私は内側と外側、別々のものを使ってみた。ネジ式の方のネジを緩めれば、カバーを取り外すことができる。(*ワイヤーと革の摩擦でワイヤーがささくれ立ち指に刺さった。ワイヤーを移動させる向きに注意する必要あり)

失敗したものも載せておく。包帯を巻いているようで、何だか変。

サイドブレーキは凹凸があり、どうしたら型紙をピッタリ作れるのだろうか悩んだ。試行錯誤し、結局は長方形にした。小さく作り、革と糸の伸縮で締めつけるのが一番簡単と考えた。

せっかくオープンカーを買ったのだから、屋根を開いて開放感を味わうのが醍醐味と思っているが、日差しの強さは予想を遥かに超えていた。
とりあえずサンバイザーを作ってみた。

しかし、そんなものでは到底太刀打ちできず、顔も腕も焼け、炎症を起こしてヒリヒリする。
「オープンカーの老夫婦、熱中症で死亡」というテレビ・テロップと、人々が嘲笑う姿がふと頭に浮かんだ。
よし、日除けを作ろう!と材料選定に数日要し、ここにも革を使うことにした。
支柱を2本、前と後ろに入れている。ダイソーの園芸用グラスファイバー180㎝(2本110円)を半分(90㎝)に切った。

前方の固定は、ダイソーの荷締めベルト(2本110円)を4本使い、サンバイザー4か所に引っ掛けて締めている。両橋はサンバイザーのストッパーに引っ掛けてあるだけ。
後方の見えるところには革ベルトを作って固定。バックルはmont-bellのものを使用。2つで352円。

気になっていたのは、頭頂部が天井に触れること。帽子を被っていると思えばいいと走行テスト。すると風を孕んで天井が膨らみ、僅かではあるが頭頂部から離れるではないか。信号待ちで停車すると再び頭頂部に触れるが、面白い発見をした。
風圧にサンバイザーが耐えられるか心配があるが、サンバイザーの支柱が外れてしまったという話も聞かないので、大丈夫だろうと考えることにした。
買い物の時、短い時間であれば、電動で屋根を閉じなくても(面倒なので)、この日除けに窓を上げておくだけで、車から離れられるような気がする。鳥の糞対策としても効果がある。
革のサイズを記しておく。90㎝✖️65㎝だが、重ねて縫い合わせた部分が2㎝程あるため、出来上がりは88㎝✖️65センチになっている。前の90㎝の支柱の両側が少し革からはみ出している。
停車時でも天井が頭頂部に触れないよう、縦に支柱を入れることも考えられるが、構造が複雑になることと収納が面倒になりそうなので、今回は見送った。
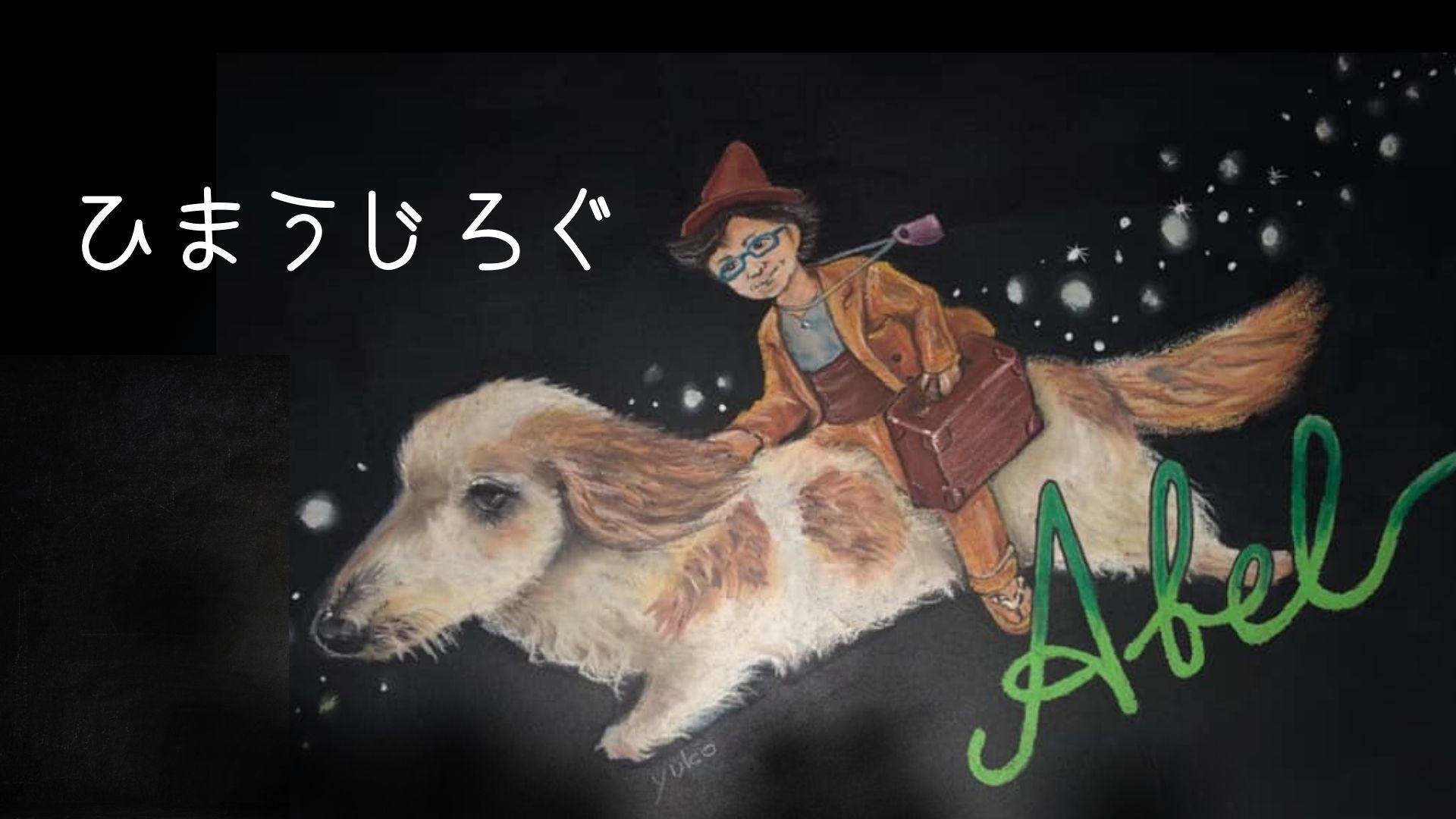



コメント