また一つ、馴染みの居酒屋が店を畳んだ。
初めて「やよい」の暖簾をくぐったのは、10年ほど前、仕事の関係で酒を酌み交わした人に誘われてのことだった。

その後、一人で通うようになり、足が遠のくと電話がかかってくるくらいになった。
閉店の理由は、女将の年齢的なことで、米寿を超え少し疲れている様子を目にすることもあった。
やよいの焼き物には、七輪の炭火が使われる。時間がかかる。その間は女将との会話が中断する。

10月30日をもって店を閉じることを聞いたのは、2日前だった。
閉店の日、翌日仕事だったが、最後だと思ったら無性に女将の料理が食べたくなった。電車を使わず家から歩いて1時間。開店よりも早く着いてしまった。
汗をかいたのでビールをいただく。

そして「いつものね」と注文すると、鰻の肝が焼き上がった。これで最後だと思うと、山椒を振りかける勢いも増す。

「今日は最後だから食べるよ〜」というと、ねぎまが焼き上がった。炭火焼きは違うなと思う。

在庫が少なくなった冷蔵庫を覗き込み、「もう最後だから日本酒は置いてないよね」と聞くと、「あるよ」と「登呂の里」特別純米が出てきた。
萩錦酒造は、女将の親戚筋にあたる。
鰤を焼いてもらう。

鮭も焼いてもらおう。

あとは女将の話に耳を傾ける。
大正時代に祖父がカフェを始めた。町は木都として栄え、人の往来が激しかったが、飲食する店はあまりなかった。
その後、居酒屋に転身し、女将は20代で母親と店を切り盛りするようになった。「女性の仕事が限られていた時代ですよ」
若き日の本田宗一郎が近くのモータースを訪れ、サイドカーの試作をしていた話、山田洋次監督が店を訪れた話などは何度聞いても面白い。
最終日だからさぞかし店は混雑するだろうと家を早く出たが、帰りがけにやっと一人、初めてという客が暖簾をくぐって入ってきた。
どこかで見たことがあると思ったら、10年ほど前に他の居酒屋のカウンター席で知り合い、酒を酌み交わした人だった。
焼酎ロックをご馳走になる。不思議な縁だ。
女将に聞けば、最終日のことは誰にも伝えていないと言う。私が知ったのも偶然である。「静かに姿を消そうと思う」
その一方で、「体力が回復したら、おでんだけの小さな居酒屋を始めたい」と言う。

「若い頃はさぞかし可愛かったでしょうね。色々なご縁があったでしょう」と言って、若い頃の話に耳を傾ける。

世界長酒造のポスターの女性のようだったのかなと想像した。
翌日、二日酔いの中で、女将の引越し先を聞き忘れたことに気がついた。携帯電話をもっていないので、こちらから電話することは叶わない。
「また連絡しますね」「会いたい人がいるから車に乗せていってくださいね」
もちろん了解したが、もしかしたら私にも連絡せずに姿を消したかったのではないかとも思えてきた。
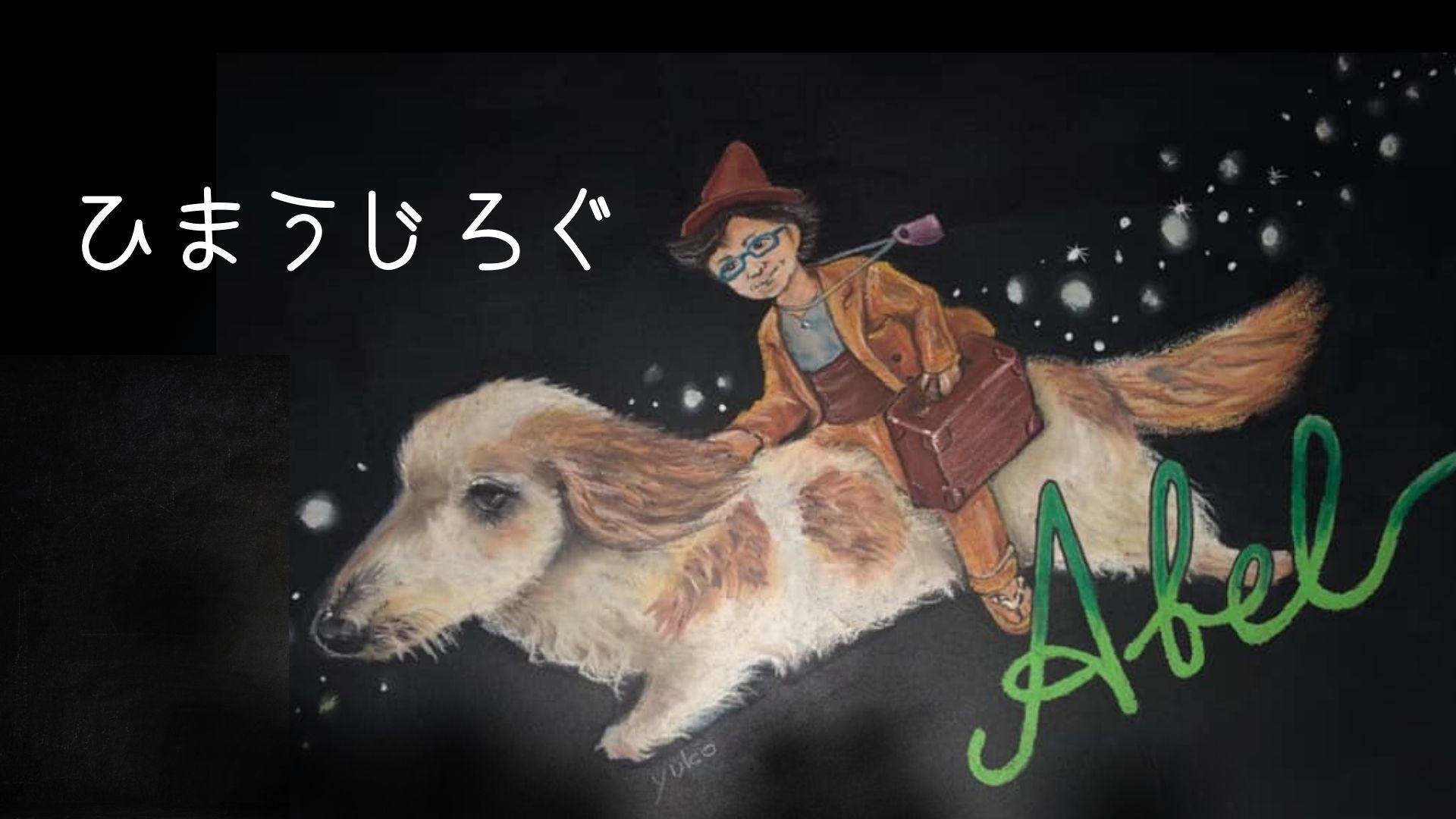



コメント